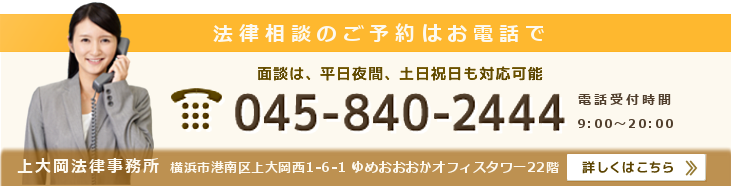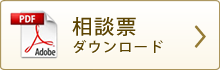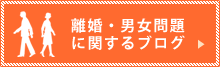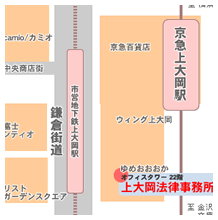裁判離婚

裁判離婚とは、離婚を成立させるかどうか、離婚を成立させるとしてその条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)をどうするかを裁判官が決める手続です。
合意によって離婚を成立させる協議離婚や調停離婚で決着がつかない場合に、この裁判離婚の手続を行うことになります。
裁判離婚の手順
離婚の理由や求める条件などを書いた訴状を家庭裁判所に提出します。
戸籍謄本や調停不成立証明書等を添付する必要があります。
裁判所の管轄は、夫または妻の住所地を管轄とする家庭裁判所です。
裁判離婚が認められるためには法定の要件を満たす必要があり、財産分与や慰謝料などについては必要な立証活動を行わなければなりません。
法律知識がないために離婚が認められなかったり、もらえるはずの財産分与をもらえなかったりする場合がありますので、専門家である弁護士に依頼した方がいいでしょう。
裁判離婚の期間
裁判離婚は、短くても数か月かかります。
複雑な事案の場合や、家庭裁判所での判決が出た後に不服申立(「控訴」、「上告」といいます。)がなされた場合は、判決が確定するまで3~4年かかることもあります。
和解離婚
離婚裁判を提起した場合でも、その裁判手続の中で、和解(話合い)によって離婚をすることができます。これを和解離婚といいます。
離婚裁判は判決(裁判)がなされるまでに長期間を要しますが、裁判手続の途中で和解離婚が成立すれば、早期に離婚ができます。
和解離婚では、離婚することのほか、親権者の指定、養育費、財産分与等の金銭給付など離婚における条件についても合意をすることができます。
離婚裁判の流れ
離婚裁判の提起から離婚届の提出までの流れを簡単にまとめると次のようになります。
(1)家庭裁判所に訴状を提出
離婚裁判(正式には離婚「訴訟」といいます)は、家庭裁判所に「訴状」を提出することによって始まります。
訴えを起こす側は「原告」と呼ばれ、訴えを起こされる側は「被告」と呼ばれます。
訴状を提出する裁判所は、夫婦のどちらの住所地を管轄する家庭裁判所でも構いません(人事訴訟法4条1項)。
夫婦が既に別居しており、原告が神奈川県横浜市、被告が北海道札幌市に住んでいる場合は、横浜家庭裁判所と札幌家庭裁判所のどちらにでも訴訟を提起することができます。
家庭裁判所に訴状を提出する際には、調停不成立証明書と夫婦の戸籍謄本を一緒に提出する必要があります。
多くの事案では、調停段階では弁護士に依頼をしていなかったとしても、訴訟を提起する段階では弁護士に依頼をして代理人となってもらい、訴状作成をしてもらうことが多いと思います。
訴訟は調停と異なり、「人事訴訟法」や「民事訴訟法」といった法律上のルールが厳格に適用されます。裁判所の職員は原告被告どちらか一方の味方をすることができないので、「分からないことは弁護士に相談してください」と言われてしまいます。
(2)訴状の送達
訴状を受け取った家庭裁判所は、まず「訴状審査」を行います。訴状に不備があれば、裁判官は原告に対してそれを直すこと(「補正」といいます)を命じます。
訴状に問題がなければ、家庭裁判所は原告の都合を聞いた上で第1回口頭弁論の日時を決めます。
その上で、家庭裁判所は被告に訴状を「送達」します。
この郵便は「特別送達」という方法によりおこなわれますが、裁判という重要な手続を行う上で、本人に確実に訴状等を届ける必要があるためです。
これを受け取らないと、家庭裁判所から訴状が被告の職場に送られてくることもあるので、無視をしてしまうとリスクが大きいです。
家庭裁判所から送られてくる郵便には、訴状と一緒に、「口頭弁論期日呼出状」と、訴訟で被告となった側が注意すべき点を解説した書面が入っています。
口頭弁論期日呼出状には、第1回口頭弁論が行われる日時と、「答弁書」の提出期限が書いてあります。
だいたい第1回口頭弁論期日の1週間前ですが、これは必ずしも厳密な期限ではなく、第1回口頭弁論の際に家庭裁判所に実際に行って提出しても有効です。
とはいえ、裁判所が指定した日時はきちんと守った方が、裁判官に悪い印象を持たれずに済みます。
(3)答弁書の提出
被告が調停時に弁護士に依頼をしていなかったとしても、訴訟になって答弁書を提出する段階では、弁護士に相談・依頼をした方が、不当に不利になってしまうリスクを防ぐことができます。
第1回口頭弁論期日は、被告の都合を聞かないで決められてしまいますので、その日時に既に別の予定が入っていてどうしても出席できないことがあります。
その場合には、事前に答弁書を家庭裁判所に提出しておき、期日に出席できないことを家庭裁判所に伝えておけば、家庭裁判所は被告が第1回口頭弁論期日に欠席することを基本的には認めてくれます。
被告が弁護士に手続を委任した場合には、弁護士が被告本人に代わって答弁書を作成して裁判を進めるのが通常で、第1回口頭弁論期日には被告本人は出席する必要はありません。
被告が依頼した弁護士も、第1回口頭弁論期日には出席しないことが多いです。
(4)第1回口頭弁論
第1回口頭弁論期日は、原告の都合を聞いて日時が決められていますので、原告はその日時に家庭裁判所に出席する必要があります。
既に原告が弁護士に依頼して訴状を作成してもらった場合には、その弁護士の都合を聞いて家庭裁判所は期日を決めます。
この場合、その期日には原告代理人弁護士だけが出席すればよく、原告本人は出席する必要はありません。
原告被告双方に代理人弁護士が付いた事案では、近時では「Web期日」といって、「Teams」というソフトウェアを使用して訴訟が進行することがよくあります。
決められた日時に裁判官と原告被告双方の弁護士がWeb上でお互いの顔を見ながら訴訟期日が行われるもので、原告被告の弁護士は自身の事務所にいながら訴訟を進めることができます。いわゆる「コロナ禍」以降に始まった制度ですが、コロナ禍が終わった後も多くの弁護士がこのWeb期日で訴訟を進めています。
第1回口頭弁論以降は、原告被告双方が「準備書面」という名前の書面で主張、反論を繰り返して行い、証拠を提出することになります。
原告が提出する証拠は「甲号証」と呼ばれ、被告が提出する証拠は「乙号証」と呼ばれます。「甲1号証」、「乙5号証」というように、提出した順に番号を付けます。
第1回口頭弁論期日の後の訴訟は、通常は1か月に1回程度の頻度で行われます。
家庭裁判所の裁判官は多くの事件を担当しており、原告被告の弁護士も多くの事件を抱えているので、それぞれが順番に事件を処理していくためにそのくらいの間隔が空いてしまうのが通常です。
(5)原告被告本人尋問
原告被告双方の主張が出尽くした段階で、原告と被告に対する本人尋問が行われるのが通常です。
もっとも、直ちにこれが行われるとは限らず、「和解」の話が進むこともよくあります。この辺りは担当する裁判官の個性が進行に大きく影響します。
本人尋問が行われる場合には、尋問期日前に原告被告双方が「陳述書」という書面を裁判所に提出します。これは、双方の主張を口語体で記載したもので、これまで訴状、答弁書や準備書面で主張したことを裏付ける証拠となるものです。
本人尋問は、Web期日ではなく家庭裁判所の法廷で一般人が傍聴できる法廷で行われます。
実際の尋問では傍聴人はほとんどいませんが、たまに裁判所見学の学生等が集団で来ていることもあります。
尋問においては、事前に提出した陳述書と「矛盾」することを言ってしまうと、裁判官としては「この人の言うことは信用できない」と判断し、敗訴してしまう可能性が高くなってしまうので、陳述書の内容はよく理解しておくように事前の注意が必要です。
本人尋問が行われた後、裁判官が双方を別室に呼んで「和解」の話をすることがよくあります。
尋問を聞いた裁判官としては、どのような判決とするか決めている(「心証を得た」といいます)場合がほとんどですが、判決となる場合にどちらの言い分が認められるかをはっきりと言う裁判官とそうでない裁判官がいます。
この和解の話は、本人尋問当日で終わることもありますが、日を開けて何回か行われることもあります。
(6)判決言い渡し
和解ができない場合には裁判官は判決を宣告することになります。これは審理が終了してから通常1~3か月程度後に行われます。
判決宣告の日時は審理終了の際に裁判官から原告被告双方に伝えられます。
判決宣告に際しては、原告被告本人や代理人弁護士は裁判所に行く必要がありません。
裁判官は法廷で判決主文を読み上げ、理由が書いてある判決書は郵便で原告被告(代理人が付いている場合は弁護士事務所)に郵便で送られます。
判決宣告に弁護士が出席しない場合でも、判決宣告後に弁護士が家庭裁判所に電話をすれば、裁判所書記官が判決主文を教えてくれるのが通常です。
判決の内容に不服がある側は、高等裁判所に控訴、最高裁判所に上告の申立てをすることができます。
もっとも、訴訟が判決まで行くことはあまり多くはなく、原告被告双方が合意して和解で終了することが多いです。
そこにおいては、裁判官や原告被告の代理人弁護士が、判決となる場合の見通しを依頼者に伝えて、和解で事件を終了させることのメリットやデメリットを依頼者に説明することがよく行われます。
(7)離婚届の提出
判決に対して原告被告とも控訴をしなかった場合には「裁判離婚」が成立し、裁判所で和解が成立した場合には「和解離婚」が成立します。
判決の場合には判決確定の日から10日以内に判決書の謄本と判決確定証明書を、和解の場合には和解成立の日から10日以内に和解調書を、離婚届と共に役所に提出する必要があります。離婚届には、他方配偶者や証人の署名押印は不要です。
協議離婚の場合には離婚届を役所に提出した日に離婚が成立しますが、判決や裁判上の和解の場合には既に離婚が成立したことを役所に報告することになります。
10日以内に提出できない場合でも役所は届出を受理してくれますが、提出できなかった理由の説明を役所から求められることがあります。
正当な理由なく期間内に届出をしないときは「過料」という制裁を受けることがありますが、そのような実例を聞いたことがありません。
最新トピックス・解決事例
-
解決事例2025/12/12
-
解決事例2025/11/07
-
解決事例2025/09/08
-
解決事例2024/07/24
-
解決事例2023/11/16
-
解決事例2023/09/17
-
解決事例2023/09/16
-
解決事例2023/07/25
-
解決事例2023/06/23
-
解決事例2020/03/04